*BL Original novel・1*
□Sweet Christmas
1ページ/1ページ
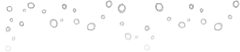
窓辺には小さな偽物のモミの木が飾られている。
ちっちゃくて可愛いオーナメントまで幾つかぶら下がっている。
部屋に差し込む陽の光にキラキラ輝いているそれは、夜になると巻かれた電飾でさらにロマンちっくなことになるんだろう。
☆ ☆ ☆
目が覚めた後、そんな敬太の隠れた乙女趣味をベッドの中から眺めていた。
キッチンの方からは、カチャカチャと何かしているらしい物音と鼻歌が聞こえる。
おでこに貼られた温くなったシップを剥がすと、布団の上にかけられていたカーディガンを羽織ってベッドから降りた。
敬太が、ふーんふふんふー♪と口ずさんでいるのはクリスマスソングだ。耳にはヘッドフォンが被せられていて、僕がキッチンに入ってきたことに気が付かない。背中から、ひょいっと手元を覗き込んでやれば、飛び上がるようにして驚いた。耳からヘッドフォンをずらしながら、
「悠也!具合どう?」
僕の顔を覗き込んできた。ふいに顔を近付けるものだから、少しかあっと顔面に血がのぼってしまった。
「まだ顔赤いね。何?喉乾いた?」
敬太は作業の手を止め、冷蔵庫を開けた。
「何してるの?」
狭いキッチンの上に置かれたボウルやら調理器具を見ても、さっぱりわからずに聞いてみた。
敬太から差し出されたポカリをぐびっと飲むと、敬太はニコニコしながら作業に戻った。
「ケーキを作ってみようかと思ってさ。っていっても、生クリームで飾りをするだけなんだけど」
僕は思わず、うへっとした思いを顔に出してしまった。
一緒に住む様になって、見た目はチャラいくせに、実は結構乙女チックな趣味に対して…の「うへっ」てのもほんの少しだけあるけれども、ただほんと、生クリームが苦手だからだ。
「砂糖抜きで作れば悠也でも食べられるかなってさ」
「なんでわざわざ苦手なものを食べなきゃならないんだよ?!」
「ええ?!だって、今日はクリスマスパーティだろ?」
パーティなんて言っても、昨日から風邪を引いてしまった僕では、どこかに出かけれられるわけでもなく、人を呼べるわけでもなく。きっと二人きりでこの部屋で過ごすことになるんだろうけれども。
敬太はボウルの中から白いクリームを一掬い、人差し指にのせた。
「味見して?」
顔の前に差し出され、思わず身を引いてしまった。
「美味しいよ?」
敬太は自分の指をぱくりと口に咥えた。甘党の敬太には砂糖抜きなんて、ほんとは嫌じゃないのかな?
またクリームののった指が差し出されると、少し申し訳ない気持ちになり、その指先をペロリと舐めた。
「どう?」
指に残ったクリームをまた自分の口に運びながら、妙に真剣な顔で聞いてきた。
「…よくわかんない」
正直、もはっとした食感しかわからなかった。砂糖がないとこんなもんなのかな?
「んー…」
ボウルの中でこんもりとしたクリームを前に、敬太は何やら考え込んだ。まさか、そこに砂糖でもふりかけるつもりじゃ…。
「まだ身体だるい?」
風邪のせいで味覚が鈍っていると思われたのかと、小さく首を振った。
「だいぶいい。寝過ぎなくらい」
敬太は僕の手をなぜだか握ってきた。
「あ、まだ少しだけ熱っぽいよ?…ベッド行こうか?」
「大丈夫だってば。何か手伝うことがあれば…」
「いいって。いいからさ…」
僕の手を引き、歩き出した敬太は、なぜだかもう片手には生クリームの入ったボウルを抱えていた。
☆ ☆ ☆
なんでもないかのようにボウルをベッドの脇に置き、
「汗かいたろ?着替える?」
なんて、ベッドに座らせた僕のパジャマのボタンに手をかけた。
いきなりの甲斐甲斐しさに戸惑う。
「いいよ、自分でやるから…」
敬太の手を外そうとした手が、握り返された。
背中から、どさり、とベッドに押し倒され、ようやく慌てた。
「け、敬太!やめ…」
「んー?」
わざとらしい呑気な声を出して、敬太はベッドの脇に置いてあったボウルに手を伸ばした。
「もっかい味見してよ。悠也のために頑張って作ったんだからさ?」
今度は人差指と中指、二本分にたっぷりと生クリームを掬ってみせた。
「い、いらないって言ってるだろ!」
企み顔の敬太から顔を横に背けるけれど、僕の身体の上に覆い被さるようにしてきた敬太は退く気配もない。
クイッと顎を掴まれた。目の前には敬太の顔が近付いてくる。敬太の唇に、白いクリームが付いている。さっきのクリームは敬太の口の中に…。
「っ…、んっ」
唇が重なり、口の中に敬太の舌と一緒にねっとりとしたものが入ってきた。舌と舌が絡み合う熱で、クリームは蕩けて喉の奥へと流れて消えていく。舌と腔内を味わい尽くすと、まだそこには味が残っているとばかりに、敬太の舌が最後に唇を舐めた。
「やっぱ甘さが足らなかったかな?」
ようやく唇を離し、ペロリと自分の唇を舐めて言った。
敬太のキスに、とろんとしてしまった自分に、ハッとなった。けれど遅かった。
肌蹴けていた胸元に、ひやっとした感触が落ちてきた。
「おいしそー!」
敬太の舌が胸の上のクリームを掬うように舐めた。
「やっ、やめっ!…ん…っ!」
クリームに隠されていた胸の突起をこりっと舐められ、思わず声を上げてしまった。
敬太は顔を上げて、ニーっといたずらそうに笑った。
「へ、へ、変態!ぼ、僕はケーキじゃない!」
「ん…、少し汗かいてしょっぱいかな…」
敬太の言葉に、羞恥でかあっと身体が熱くなった。
敬太が自分のシャツの裾に手をかけ、一気に服を脱いだ。
「クリスマスっぽくていいっしょ?」
そう言って、また一掬いクリームをのせた指先を見せてくるから…僕は急いでパクリとその指先を口に咥え込んだ。また、身体のどこかに塗られたらたまったもんじゃない!と思っただけだったけれど、目だけ上げて敬太を見れば、敬太の喉がごくりと動いた。
「…美味しい?」
風邪を引いていた僕以上に敬太の身体が熱を帯びてきた。優しく髪を撫でられ、僕もゾクリと来てしまう。
二人きりなんだし…、恋人同士なんだし……、クリスマスなんだし…。
勇気を振り絞り、
「美味しい…」
そう答えたら、……敬太の目が…キラリと光った気がした…。
裸にされた素肌に、楽しそうに敬太の指がクリームを塗りたくっていく。逃げ出したいけれど、その様子があまりにも楽しそうで、つい…甘えさせてしまった…。
せっかく塗ったクリームを敬太の舌はペロペロと舐めていってしまう。クリームが無くなった場所には、ちゅうっと吸い付き赤い痕を残す。
寝汗のままの身体の気恥ずかしさでモジモジと体を捩り、クリームの気色悪さに震え、敬太の舌の巧みさに…ムズムズと快感が湧き上がる。
はあ、っと息を吐き、体の変化を誤魔化そうとするけれど、身体の中心にヒヤリとクリームが塗られたときにはさすがに慌てた。
「や…やめ…」
「すっげー美味そう」
いちいちそんな言葉に興奮して、身体を熱くする自分がますます恥ずかしい。
すでに立ち上がったそれに、満足が行くまでクリームをまぶし、敬太は「いただきます」なんて言ってパクリと口に咥えた。
「ん…っ、あっ、ふ…っ、け、敬太…」
口の中で舐めとるように舌が動かされ、気持ちよさに腰が震える。
「あ…、た…、食べるな…よ…」
僕の台詞に、敬太は咥えたままで喉の奥で笑った。そんな刺激も堪らない。
「敬太!あ、あっ!も…、やめ…」
切羽詰ってきていることを伝えると、あっさりと敬太はそれから口を離した。
「クリーム追加!」
とか言って、もうすでに僕の横に置いてあったボウルに手を伸ばした。
「…こっちにね」
敬太は興奮して熱り立った自身のそれに白いクリームをたっぷりとのせた。
「お願い、ゆう…」
敬太を軽く睨みつけてから、渋々という態度で身体を起こした。だけど、敬太に掴まれた僕の興奮で、僕の期待はばれている。
ゆっくりと顔を寄せ、根元に手を添え、苦手だった味に口を寄せた。
「…あっ」
敬太が小さく声を上げるから、ドキンと心臓が高なった。
ペロリと舌でクリームを舐めとると、口の中にぼやけた味が広がる。甘い、甘いと思い込んでいたクリームは、実はそんなに甘くない…ということにやっと気が付いた。だから、もう一口…。
「…ゆう」
呼ばれて顔を上げると、敬太がクスリと笑った。そして、僕の鼻の頭に、ちょこっと指先で触れた。その指先をペロリと舐める。
「鼻の頭にクリームがついてた」
ふふ、と笑われ、夢中で舐めていたことに気が付いた。先端にはもうクリームは残っていない。
「あーあ、もうなくなってきちゃったなあ…」
そう言いながら、敬太が名残惜しげにボウルの中のクリームをかき集めた。
「最後のこれは…、ここに」
また敬太が自身のそこにクリームを塗った。自分の手で、ぬちゃぬちゃと音をたてるようにしてすっぽりと塗りたくった。
「俺の、まだ食べるっしょ?」
何を言っているのかと思ったら、両脚をガバリと開かれて、脚の間に腰を進められて意味がわかった。
「まだ少し熱っぽいかな…?つらい?大丈夫かな…?」
そこまでやっておいて、わざとらしく心配してみせるからカチンとくる。
「は…、はやくしなきゃ…、とけちゃうだろっ!」
敬太が小さく笑った気がした。
胸を重ね、唇は唇に塞がれて、身体の奥の場所に、熱いものが押し当てられた。クリームのぬめりで、それは容易く中へと侵入してきた。
「ん…、ん……っ」
僅かに唇を離した敬太が囁いた。
「…悠也の中、あまーい」
敬太の首に両腕を回し、引き寄せるようにしてもう一度唇を重ねた。そして、ズンッとした衝撃と共に、身体が深く繋がった。
……ほんとに…、とけてしまいそうなくらいに…、クリームは甘い…って思った…。
くちゃりと恥ずかしい音は、興奮とクリームが混ざった音だ。ぬるりとする身体は、熱とクリームが混ざった汗だ。
身体の奥に熱いものが溶け出す感触に、腹の上にもとろけ出したものが溢れ出た。
「悠也…っ!…くっ!」
「んっ!……はぁ…、はぁ…」
荒い息のまま、まだ、奥に埋めたままの敬太が僕の臍の上を手で探る。
「これも甘いかな?」
吐き出した僕の興奮を指先で掬い、それをペロリと舐めるから、全身に血が駆け巡って、敬太にしがみついた。クリームに似ているけれど、それは…。
「甘い」
「バ、バカ!」
部屋は、薄暗闇に包まれ始め、外の商店街のネオンが部屋の中に差し込んでくる。
「敬太…、も…、いい加減…」
「ん…」
名残惜しそうに身体を引き抜かれ、ブルッと身体が震えた。
まだお互い、欲情は残っているけれど、今夜はまだ、長いから…。
☆ ☆ ☆
ベタベタの身体が気持ち悪くて、急いで裸のままシャワーに駆け込んだ。
部屋に戻ると、敬太は、汚れたシーツを剥ぎとり、いそいそと新しいシーツに換えている。ほんと、まめな奴だ…。
「あ、浴びてきた?じゃ、俺も…」
裸のままの敬太は立ち上がり、ちらりと僕を覗った。
「ごめ…、あの…、体調平気?」
謝るくらいならするな!って怒ってやろうと思ったけれど、そんなに気分も悪くない。すっかり風邪は治ってしまったようだ。汗をかいたおかげだなんて、絶対に感謝はしてやらないけれども。
「早く浴びてこいよ!…買い物行かなきゃならないだろ!」
僕は腰に巻き付けていたバスタオルを敬太に向かって投げた。そのままタンスに向かって着替えを漁る。
「ん?なんか買う?料理とか一応、もう、買ってあるけど」
敬太は顎に指を当てちょっと考える。
「ケーキがなきゃ始まらないだろ!クリスマスなんだから!」
せっかくの手作りケーキはきっと台無しにしてしまったから…。
敬太はへへへっと照れたように笑ってから、
「だね。ちょい待っててね」
と言って、シャワーに向かった。
部屋の電気を付ける前に、ふと思い出して、ツリーの電飾のスイッチを入れた。
キラキラ輝くツリーを眺め、シャワーから聞こえてくる敬太のクリスマスソングに小さく笑った。
ああ、でも、生クリームののったケーキは却下してやる。
外は寒そうだから、プレゼントに用意したマフラーも、出掛ける前になら……さり気なく渡せるかもしれないな…。
(I wish you a merry and happy Christmas!)
